高額な医療費を支払ったとき
 窓口での自己負担金額は3割(または2割)が原則ですが、
窓口での自己負担金額は3割(または2割)が原則ですが、
自己負担金額が一定額を超えたときは健保から自動で支給(払い戻し)します
※市区町村等から医療費助成を受けている方については、下記のケースに当てはまらない場合があります。別途書類をご提出頂くケースもございます。(詳細はコチラ)
※未就学児への「高額療養費」「付加給付」の自動支給は原則停止しています。(詳細はコチラ)
高額療養費制度のご説明
医療機関を受診した場合、医療費が高くなるケースがあります。この場合、健康保険を適用すると3割(もしくは2割)負担ですので、自己負担額も高額となってしまいます。これに対する救済措置として、法律で「高額療養費制度」が設けられています。収入基準にしたがって一定の金額(※1)を超えた部分については後日払い戻しをする制度です。これらは自動支払いとなっていますので、申請手続きは一切不要です。
(※1)自己負担限度額表にてご確認ください。
付加給付制度のご説明
さらに富士フイルムグループ健康保険組合独自の制度として、「(先に述べた)法律で定められた一定額の自己負担額」のうち、「3万円を超える額」を健康保険から給付する「付加給付制度」を設けています。一旦支払った自己負担額と3万円との差額が還付されます。これについても自動支払いとなっていますので申請手続きは一切不要です。
払い戻し金額
以下の算定基準(※2)に基づき、自己負担額が30,000円(1,000円未満切り捨て)を超えた部分が付加給付として支給されます。
※差額ベッドや食事代など保険適用外の費用は自己負担額に含みません。
(※2)算定基準
①受診者ごと
②1か月ごと(暦月単位)
③各医療機関ごと(さらに 入院・通院、医科・歯科ごと)
例えば…
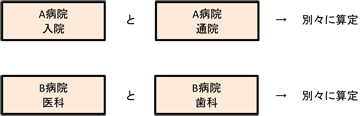
払い戻し額の計算例
a)自己負担額が30,700円
→支給なし
(30,700円-30,000円=700円⇒0円)◀1,000円未満は切り捨てます!
b)自己負担額が52,600円
→22,000円支給
(52,600円-30,000円=22,600円⇒22,000円)◀1,000円未満は切り捨てます!
払い戻しのお手続き
お手続き不要です。(自動で払い戻します)
払い戻しのタイミング
最短で3ヵ月後に支給します。(毎月 原則25日払い)
払い戻しの金額については、支払月上旬に「支給決定通知(KOSMO WEB)」でお知らせします。
| ・支給決定通知の詳細はコチラ ・ログイン等についてはコチラ |
《支払月早見表》 毎月 原則25日払
| 診療月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
Q.1月に高額な医療を受けました。健保から払い戻しがあると聞きましたが、いつ支給されますか?
A.上記「支払月早見表」の通り、原則4月25日に支給されます。
その場合4月上旬に、「支給決定通知」にて支給額を通知いたしますのでご確認ください。
払い戻しの確認のポイント
①まずは、上記「支払月早見表」で、原則の支払月を確認する
②支払月25日が未来日であれば、支払日25日まで待つ
③支払月25日から経過している場合は、「支給決定通知」や「振込口座」で、払い戻しを確認する
※払い戻しがない場合、医療機関側の手続き等が遅れている可能性があります。月初めに通知される「医療費通知(KOSMO Web)」に該当の医療機関が掲載されているかご確認ください。掲載がない場合、翌月以降に再度ご確認いただき、診療月から半年以上経過しても掲載がない場合は健保へお問合せください。
医療機関窓口での自己負担金額を抑えるには
● 医療機関側がオンライン資格確認に対応している場合
マイナ保険証等※を医療機関窓口へ提示するだけで、自己負担額を限度額(自己負担限度額表)までに抑えることができます!
● 医療機関側がオンライン資格確認に対応してない場合
「限度額適用認定証」の準備が必要です。
● 非課税者の方
別途申請が必要です。
オンライン資格確認とは、マイナ保険証等※で自己負担限度額をオンライン上で確認ができる仕組みです。
※マイナ保険証等…マイナ保険証、資格確認書、健康保険証
自己負担限度額について
69歳以下の方 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)
| 被保険者の所得区分 | 一部負担の上限額(月単位) | |
|---|---|---|
| ア | 標準報酬月額 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [140,100] |
| イ | 標準報酬月額 53万~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [93,000] |
| ウ | 標準報酬月額 28万~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [44,400] |
| エ | 標準報酬月額 26万円以下 | 57,600円 [44,400] |
| オ | 低所得者(住民税非課税者) | 35,400円 [24,600] |
※[ ]内の額は、4ヵ月目からの限度額です。高額療養費の支給が直近12ヵ月に3ヵ月以上あった時は、4ヵ月目からは限度額が下がります。
※非課税者は別途申請が必要です。
(詳細は限度額適用認定証が必要なとき)
70~74歳の方 医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)
平成30年8月診察分から
| 被保険者の所得区分 | 月単位の上限額 | ||
|---|---|---|---|
| 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
| 現役並み所得者 | 現役並みIII
標準報酬月額 |
252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% [140,100円] |
|
| 現役並みII
標準報酬月額 |
167,400円 + (総医療費-558,000円)×1% [93,000円] |
||
| 現役並みI
標準報酬月額 |
80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% [44,400円] |
||
| 一般 | 標準報酬月額 28万円未満 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 [44,400円] |
| 低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
| I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 | ||
※[ ]内の額は「多数該当」の場合、過去12ヵ月以内4回目以降の限度額。「外来のみ」は多数該当の対象にはなりません。
※年間上限は、8月1日から翌年7月31日までの間の合計
※富士フイルムグループ健保の特退加入者は現役並みⅠとなります。
さらに自己負担が軽減される場合
世帯単位で自己負担額を合算(合算高額療養費)
・1ヵ月1件ごとの自己負担額が限度額に満たなかった場合でも、次の条件で支給となります。
同一月・同一世帯で21,000円以上のものが2件以上あった場合(計算例はコチラ)
多数該当の場合
・同一世帯で直近12ヵ月の間に高額療養費が4回以上になった場合、4回目からの自己負担の限度額が引き下げられます。(下記「医療費の自己負担限度額」月単位の上限[]内参照)
多数該当
多数該当になるには、医療を受けた月以前の11ヵ月間に、3回以上高額療養費に該当している必要があります。
《多数該当となる月の数え方(例)》
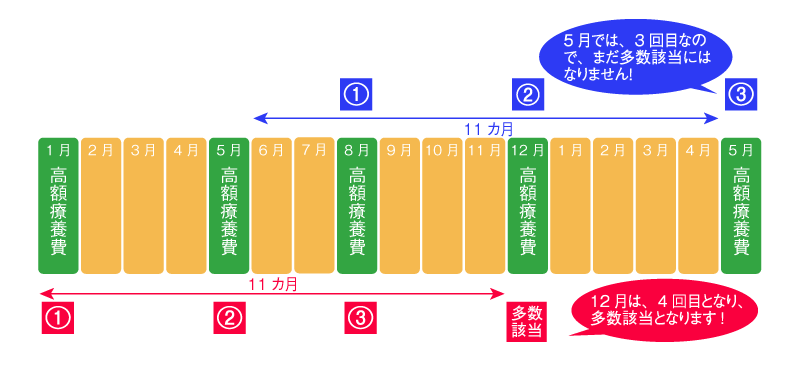
※同じ保険でも被保険者が変わった場合や、保険制度が変わった場合は、高額療養費の回数は引き継ぎしません。
例:【被保険者の変更】 本人→被扶養者 【保険制度(保険者)の変更】 富士フイルムグループ健保→他健保
特定疾病の治療を受けている場合
治療を要する期間がきわめて長く、かつ治療費が高額になる病気については、厚生労働大臣が「特定疾病」と認定し、負担を軽減する制度もあります。(詳細はコチラ)
高額療養費の計算例
合算高額療養費の計算例:1
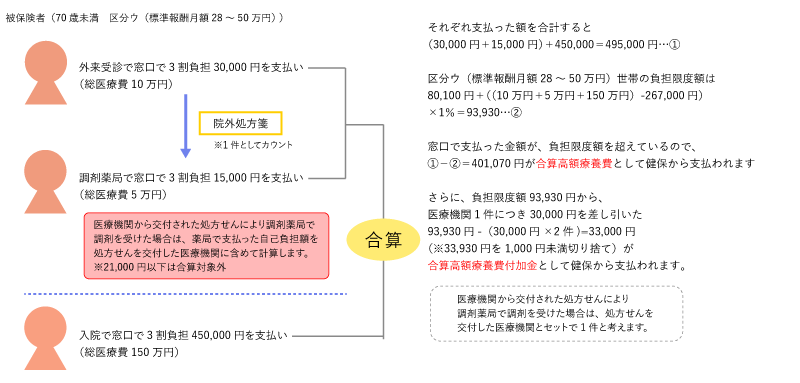
合算高額療養費の計算例:2
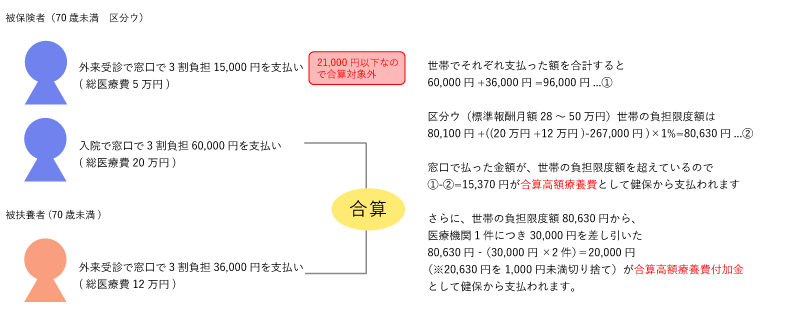
合算高額療養費の計算例:3
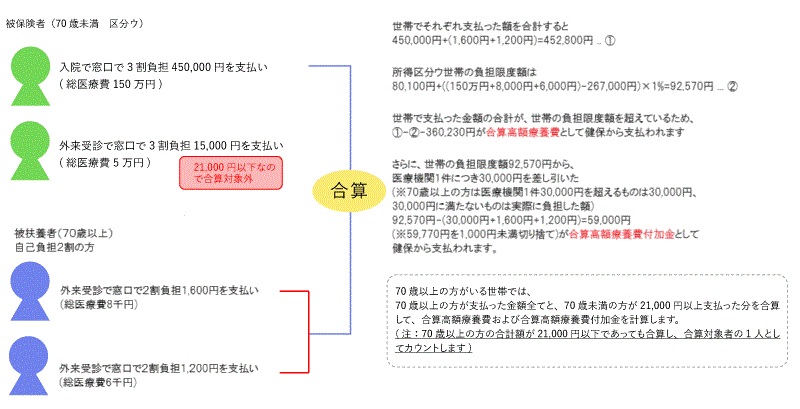
合算高額療養費の計算例:4
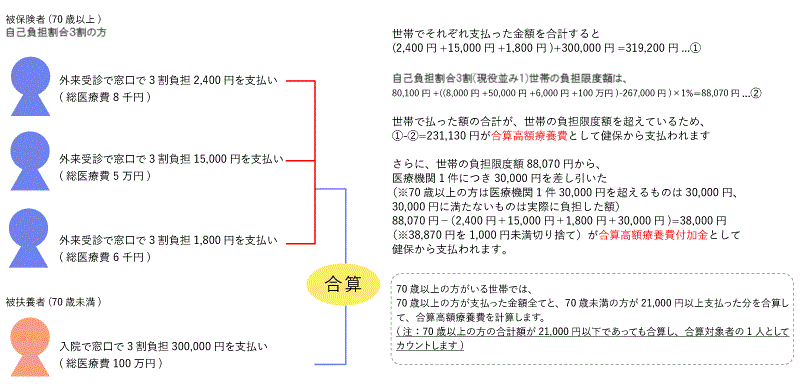
高額医療費貸付制度
高額療養費の支給には、医療機関での支払いから3ヵ月ほどかかります。それまでの間、高額療養費の8割相当する額を無利子で借りられる制度です。
※医療機関での支払いが既に自己負担の上限額に抑えられている(高額療養制度が適用されている)場合は、この制度は利用できません。
| 対象者 | 被保険者および被扶養者 |
| 貸付の条件 | ①同一人が同一月内に同一医療機関の窓口で負担した額が「月単位の上限額」を超えて高額療養費の該当となること ※「月単位の上限額」は標準報酬月額により異なります。前記「医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)」の一覧表を参照してください ②申請の時期が高額療養費の払い戻し決定以前(概ね2ヵ月以内)であること ※3ヵ月後には高額療養費の払い戻しがあるため |
| 手続き | ①「高額療養費資金貸付申込書」に保険適用の総医療費の内訳のある請求書か領収書の写しを添えて健保へ提出 ②貸付が決定後、健保より「貸付可否決定通知書」「借用書」が送付され、被保険者の指定口座に貸付金が振り込まれます。 ③健保から送付された「借用書」に必要事項を記入・捺印・収入印紙を貼付の上、返送してください。 ④自動払いされる高額療養費から貸付額を引いて清算されます。清算後には健保から「借用書」を返却します。 |
| 貸付額 | 高額療養費支給見込み額の8割相当(1,000円未満切捨て)です。 |
| 返済方法 | 高額療養費の支給額と貸付額を相殺した額が支給され返済完了となります。 |
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトし、必要事項をご記入の上提出してください。
- 添付書類の有る物は、モレが無いか必ずご確認ください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
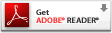
Word・Excelファイルに関する注意事項
- Internet Explorer(以下IE)のサポート終了に伴い、当ホームページはIEでの閲覧を推奨しておりません。
IE11で利用した際に生じた不具合についてはお問合せいただいても、お応えすることができません。予めご了承ください。